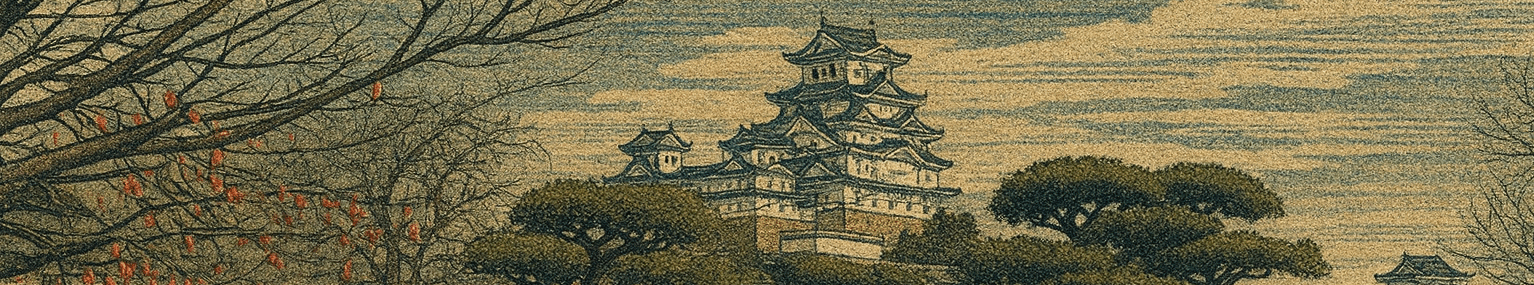今回は夏休みを利用して、瀬戸内周辺の城巡りをしてきました。まず最初に訪れたのは、岡山城です。
岡山城では、8月限定で「夏の烏城灯源郷」というライトアップイベントが開催されています。普段は18時までの開館時間ですが、イベント期間中は21時まで天守閣に入場することができます。
今回は夜に岡山に到着したため、まずはライトアップされた夜の岡山城を訪れてみました。闇夜に浮かび上がる黒漆塗りの天守は、「烏城(うじょう)」の名にふさわしく幻想的で、美しく照らされた石垣や城門も見ごたえがありました。

天守閣を中心に、城内の各所が美しくライトアップされており、幻想的な雰囲気の中を登城していきます。
特に、本丸本段では、天守閣を中心に広がる空間全体が照らし出されており、その光景はまさに圧巻でした。

さっそく夜の天守閣に入ってみました。復興天守ということもあり、上階へはエレベーターでアクセス可能です。真夏の蒸し暑い夜だったので、階段を使わずに済んだのは本当に助かりました。
こちらが天守の最上階です。令和の大改修を経ているだけあって、内部は非常に整備されており、清潔感と現代的な快適さがありました。

金鯱にライトが当たって輝く様子と、天守閣から眺める夜景の組み合わせは、まさに「夏の鳥城灯源郷」開催期間中ならではの醍醐味です。

天守閣の各階層には、岡山城の歴代城主である宇喜多氏、小早川氏、池田氏に関する展示が設けられていました。また、展示内容は歴史マニアだけでなく、家族連れでも楽しめるように工夫されており、ミニシアターなどもあって、子どもでも理解しやすい内容になっていました。
天守の観覧を終えたあとは、隣接する後楽園にも立ち寄ってみました。昼間の様子はわかりませんが、夜は岡山城のライトアップに合わせて庭園全体が美しく照らし出され、幻想的な雰囲気を楽しめました。

さて、翌日の早朝には、明るい時間帯の岡山城にも登城してきました。今回は、岡山城の正面にあたる大手側からのルートを選び、目安橋を渡って登城していきます。

橋を渡った先、本丸への入口付近には、いくつかの鏡石が置かれていました。

この岡山城は、豊臣政権下で宇喜多秀家が城主で、江戸時代には徳川家譜代の池田忠継が藩主となった城でもあります。こうした背景から、築城技術の粋を集めた立派な石垣が今も随所に残されており、両時代の威光を感じさせる構えとなっています。
こちらは、大納戸櫓および本丸中の段の石垣です。この石垣は、小早川秀秋の時代(江戸時代初期)に築かれたもので、特徴としては自然石をあまり加工せずに積み上げている点が挙げられます。

そのまま奥へ進むと、本丸本段の石垣が現れます。こちらは宇喜多秀家時代に築かれたもので、関ヶ原の戦い以前に築かれた石垣としては、全国でも屈指の高さを誇るそうです。築城技術が成熟する前の時代にこれほどの規模を実現していたことからも、当時の宇喜多氏の権勢と技術力の高さがうかがえます。

不明門を通って本丸本段へ向かいます。この門は、普段は使用されず、常に閉じられていたことから「不明門(あかずのもん)」と呼ばれるようになったのだそうです。

昼間の岡山城は、夜の幻想的な雰囲気とは一転して、堂々たる壮大さを感じさせます。その黒塗りの外観は、まさに「烏城」の名にふさわしく、青空を背景にした姿は圧巻です。

本丸本段から中の段へ戻ると、そこには発掘調査で見つかった築城当時の石垣が展示されていました。この石垣は、中の段を拡張する際に埋め立てられていたものだそうで、当時の姿を今に伝える貴重な遺構です。

こちらは本丸の搦手に位置する廊下門です。この門は、本丸本段と中の段をつなぐ通路にあたる位置にあり、城主専用の廊下としても使用されていたことから、「廊下門」と呼ばれるようになったそうです。

こちらは現存建築物の月見櫓です。この櫓は非常に珍しい構造をしており、城外から見ると「二層の望楼型」に、城内から見ると「三層の層塔型」に見えるという造りになっています。

また、岡山城にはもう一基の現存櫓があります。それがこの 西丸西手櫓です。こちらの櫓は、烏城公園の中心部からやや離れた場所にあり、観光ルートから少し外れた駐車場の奥に静かに建っています。

朝と夜で異なる表情を見せる岡山城。天守閣内の展示はもちろんのこと、城内の各所には丁寧な説明板が設置されており、歴史に詳しくない方でも十分に楽しめるようになっています。
特に夏限定のライトアップイベント「夏の烏城灯源郷」では、幻想的な雰囲気の中で城を巡ることができ、昼間とはまったく異なる魅力を味わえます。
歴史の重厚さを感じる朝の雄大な岡山城と、幻想的な光に包まれる夜の岡山城。その二面性を一度に味わえるこの夏、みなさんもぜひ「烏城」へ訪れてみてはいかがでしょうか。