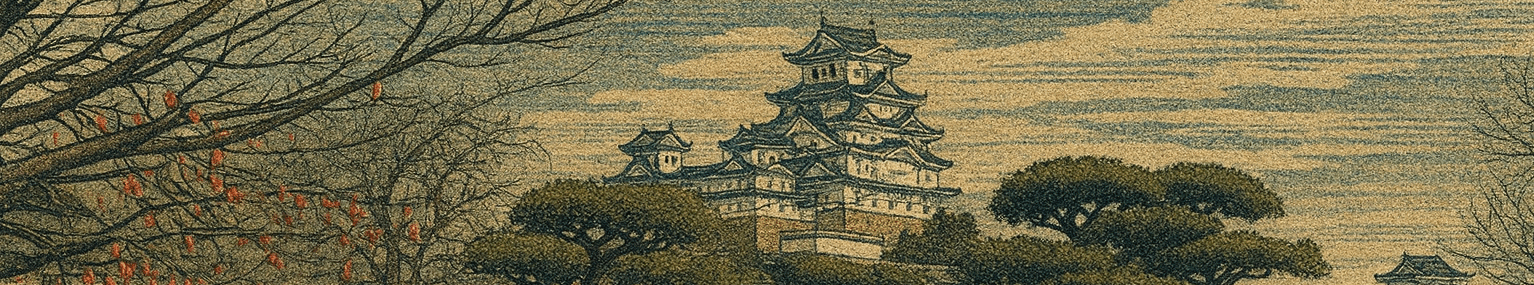日本100名城の中でも珍しい、弥生時代の遺跡「吉野ヶ里」を訪れました。ここは邪馬台国の候補地の一つともいわれるほど広大な集落跡で、現在は「吉野ヶ里歴史公園」として整備されています。

吉野ヶ里遺跡では、弥生時代の集落の様子がこのように忠実に再現されていました。

当時は、集落の周囲に尖った木の杭を並べてバリケードを築き、外敵から身を守っていたといわれています。
遺跡の内部に進むと、まず「南内郭」があります。ここは集落の南側の防御を担っていた区域で、当時は見張りや守備の拠点として機能していたと考えられています。

南内郭には竪穴式住居のほか、櫓や集会所などが復元されており、弥生時代の暮らしを身近に感じることができます。とくに竪穴式住居の内部には、人形が配置され、当時の生活の様子がリアルに再現されていました。

さらに進むと「北内郭」にたどり着きます。ここには当時の王や有力な指導者が暮らす宮殿があったとされ、集落の政治や祭祀の中心地だったと考えられています。

入り口には目隠しが設けられており、外部から中の様子が見えないようになっていました。この造りからも、特別な地位を持つ人々がここで生活していたことがうかがえます。
北内郭の中でもひときわ目を引くのが、この「主祭殿」です。16本もの太い柱で支えられた、吉野ヶ里遺跡で最大規模を誇る建物で、当時は祭祀や重要な集会が行われていたと考えられています。
まさに、弥生時代の“天守閣”といった風格を感じさせる建物です。

主祭殿の内部では、当時の指導者たちが重要な決定や祭祀に関わる話し合いを行っていたといわれています。展示では、その様子が人形や復元された調度品で再現されており、弥生時代の政治や社会の姿をリアルに感じ取ることができました。

さらに主祭殿の最上階では、巫女が神からお告げを授かる神聖な儀式が行われていたと伝えられています。もしここが邪馬台国の跡であるならば、もしかすると卑弥呼もこの場所で祈りを捧げ、神託を受けていたのかもしれません。

北内郭の周囲は、二重の柵と空堀によって厳重に守られていました。敵の侵入を防ぐための堅牢な防御施設で、弥生時代の集落がすでに後世のベースとなる防御技術を備えていたことがわかります。

北内郭の奥には、「北墳丘墓(きたふんきゅうぼ)」と呼ばれる古墳が残っています。これは歴代の王や有力な支配者たちの墓であったと考えられています。

この北墳丘墓からは、「甕棺(かめかん)」と呼ばれる素焼きの棺が14基も発見されています。弥生時代には、亡くなった人をこの甕棺に納めて土中に埋葬する風習があったんだそうです。

吉野ヶ里遺跡には、王や貴族の居住区以外にも、市や倉庫跡が残されています。このエリアには住居とは異なり、高床式の建物が多く、穀物や物資を保存したり、交易や祭祀の場として利用されていたと考えられています。

さらに、当時の庶民が暮らしていた集落(ムラ)も復元されています。このムラには、複数の家族が竪穴式住居で共同生活を営んでおり、狩猟や農耕、物々交換を行いながら暮らしていたと考えられています。

吉野ヶ里遺跡では、遺跡の見学だけでなく、火おこしや勾玉づくりなどの体験プログラムも楽しめます。
いわゆる「お城巡り」とは少し趣が異なりますが、弥生時代の生活や文化に触れ、古代のロマンに思いを馳せてみるのもおすすめです。