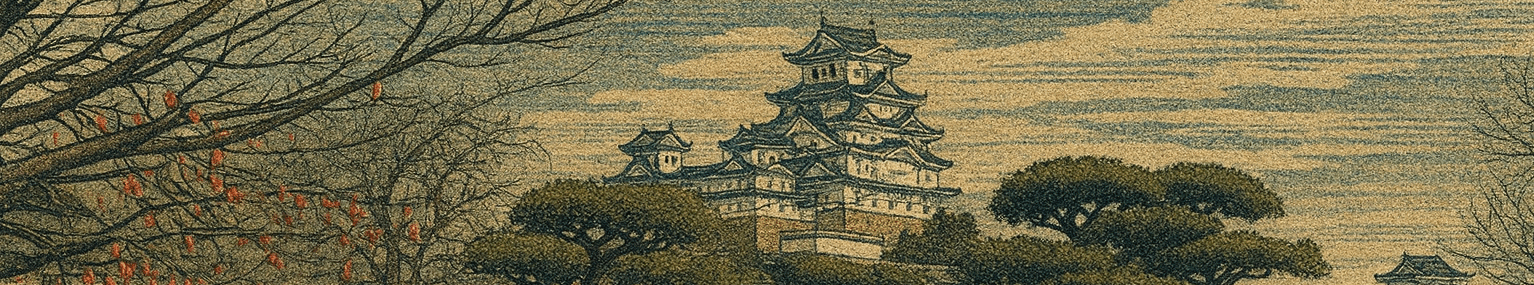鍋島氏の居城として知られる佐賀城に行ってきました。佐賀駅からはやや距離があるため、今回はレンタサイクルで向かうことにしました。
佐賀城に到着してまず目に入るのが、威風堂々とした「鯱の門」です。この門は、佐賀藩10代藩主・鍋島直正によって建てられたもので、現在も当時の姿を残す貴重な建築です。

鯱の門には、1874年に起きた「佐賀の乱(佐賀の役)」の際に刻まれた銃痕が今も残っています。明治維新後の動乱を物語る生々しい痕跡で、当時の激しい戦いの様子が想像されます。

本丸跡には「佐賀城本丸歴史館」が建っています。ここはかつての本丸御殿の一部を忠実に復元した施設で、当時の御殿の約3分の1にあたる規模が再現されています。

まず天守台に登ってみようと思いましたが、佐賀城の天守台へは本丸から直接登ることはできません。現在は二の丸側からのみ登れるようになっているため、裏手の西門を通って一度城の外に出る必要があります。

こちらが佐賀城の天守台です。かつては4層5階建ての壮大な天守がそびえていましたが、享保11年(1726年)の大火で焼失し、その後再建されることはありませんでした。

実際に天守台に登ってみると、その広さに驚かされます。かつてここに4層5階の天守が建っていたことを考えると、佐賀城がいかに大規模で威容を誇っていたかがよくわかります。

天守台に登って周囲を見渡すと、佐賀城の塀の構造がよくわかります。外側は堅牢な石垣で造られていますが、内側は土塁になっており、石垣と土塁を組み合わせた独特の防御構造となっていました。

本丸御殿の裏手には、石で造られた水路が残っていました。かつてはここから本丸内に水を引き込んでいたといわれています。当時の城内インフラを今に伝える貴重な遺構です。

本丸の裏手に回ると、土塁と堀がしっかりと残っています。

本丸を一通り見学したので、本丸御殿(佐賀城本丸歴史館)に入ってみました。
復元された本丸御殿は、当時の規模を忠実に再現しており、長く広い廊下や、藩主が政務を行った広大な部屋が並んでいます。

実際に歩いてみると、まるで江戸時代にタイムスリップしたかのような気分を味わえ、当時の藩主や家臣たちの暮らしぶりが想像できます。
こちらは藩主の仕事部屋である「御座間」です。

もともとは鍋島直正が建てた部屋で、一度は別の場所に移築されていましたが、本丸御殿の復元工事にあわせて、元の位置に再び移されました。鯱の門と並び、佐賀城に現存する貴重な建築物のひとつです。
佐賀城は遺構が本丸を中心とした範囲に限られているため、比較的短時間で見学することができます。また、名古屋城などと違い、復元された本丸御殿を自由に歩き回れるのが大きな魅力でだと思います。
みなさんも、広々とした廊下や藩主の御座間を間近に体感してみてはいかがでしょうか。