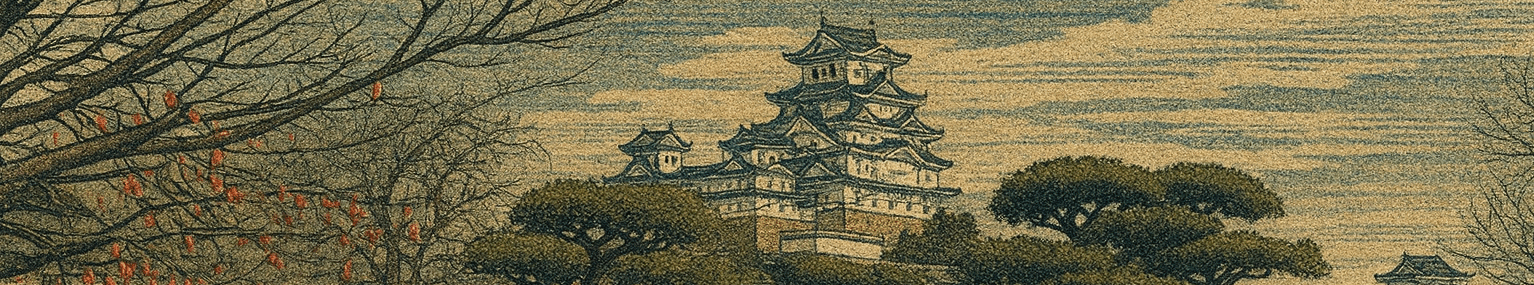瀬戸内周辺の城巡り、三つ目は海城として有名な高松城に行きました。多くの城が高台に築かれているのに対し、高松城は瀬戸内海に面して造られた珍しい海城です。現在は「玉藻公園」として整備されており、復元された櫓や美しい石垣、海水を引き込んだ堀から、当時の面影をしっかりと感じることができます。

高松駅側から公園に入ると、右手に早速天守台が見えてきます。まずは、この鞘橋(さやばし)を渡って本丸へ向かいます。有事の際には、この橋を落として本丸を守る仕組みになっていたそうで、当時の防御の工夫を感じられます。

本丸には天守台が残っています。かつてはここに三層五階の立派な天守が建っていたそうです。さらに近年の発掘調査により、地下一階も存在していたことが明らかになったそうです。

天守台には、当時の礎石が今も残っています。礎石はこのように田の字形に並べられ、区切られた4つの区画それぞれに柱を建てる独特の構造だったそうです。実際に礎石を目にすると、往時の天守の規模や造りを具体的に想像できます。

天守台からは、先ほど渡った鞘橋が本丸と二の丸をつないでいる様子がよく見えます。高い位置から眺めると、当時の城の構造がより鮮明にイメージできます。

また、海城だけあって、高松城の堀には海水が引き込まれています。二の丸と三の丸の間には、海とつながる水門が設けられていました。

こちらが水門です。潮の干満に合わせて海水が入れ替わる仕組みになっているそうで、海城ならではの工夫を感じます。

堀も海水なので、泳いでいる魚もよく見かける鯉ではなく、鯛がたくさん泳いでいました。お城のお堀で鯛を見るという、海城ならではの光景にちょっと驚かされます。

こちらは、月見櫓と水手御門です。現在は埋め立てられていますが、かつてはこの櫓の外まで海が広がっており、船でこの水手御門を通って直接城内に入ることができたそうです。海城ならではの造りを感じさせる場所です。

三の丸には、かつて披雲閣(ひうんかく)という御殿が建っていました。現在建っている御殿は大正時代に再建されたものだそうです。あいにく訪問時は工事中で、その建物の全貌までは見られませんでしたが、庭園や周囲の雰囲気から当時の面影を感じ取ることができました。

こちらの桜御門は、御殿である披雲閣の正門です。かつては国宝に指定される予定だったものの、戦時中の空襲で消失してしまいました。その後、2022年に再建されましたものが現在の門です。まだ年月が浅いため、木の色合いなどからも新しさが感じられます。

こちらは、艮櫓(うしとらやぐら)です。もともとは城の北東に建っていた櫓ですが、現在の場所に移築されたそうです。現存する月見櫓と同時期に建てられたもので、実際に目にすると当時の面影を感じることができます。

海城という珍しい構造をもつ高松城。水門や水手御門など、海と一体となった独特の造りはとても興味深かったです。皆さんも、雄大な瀬戸内の海とあわせて高松城を楽しんでみてはいかがでしょうか。