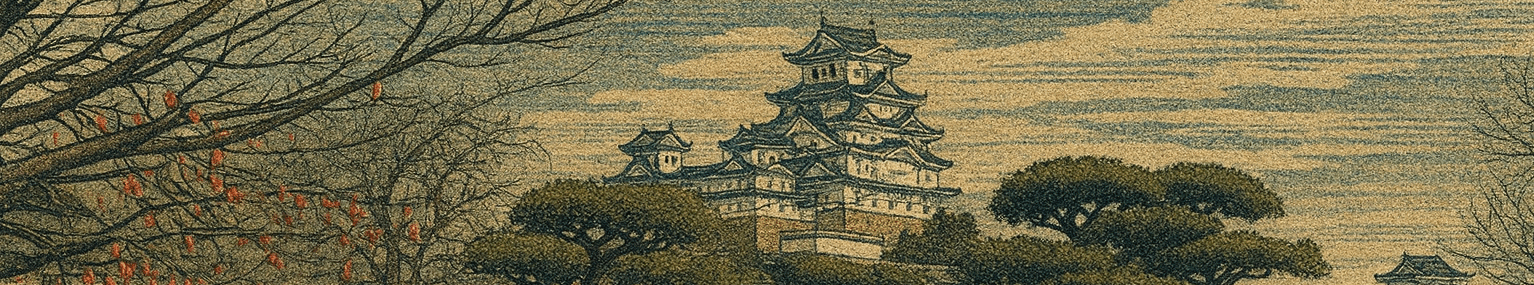黒田長政によって築かれた「福岡城」に行ってきました。現在は大濠公園として整備されており、駅からのアクセスも良く、気軽に訪れることができます。
駅を出ると、目の前に広がるのは福岡城の濠と「潮見櫓」の姿。かつて福岡城にはおよそ50もの櫓が建ち並んでいたとされ、当時の規模の大きさがうかがえます。

そのまま濠沿いに進んでいくと、「下之橋御門」が見えてきます。福岡城に設けられていた3つの主要な城門のひとつで、当時は城下町から本丸へ向かう重要な入り口として使われていたそうです。

門を通った先には、現在「牡丹・芍薬園」として整備されている一角があります。ここはかつて、福岡城を築いた黒田長政の父であり、名軍師として知られる黒田官兵衛(如水)の隠居地だった場所です。

三ノ丸は現在整備が進み、当時の面影はほとんど残っていませんが、その入口には「名島門」が移設されています。この門はもともと福岡城のものではなく、黒田長政が福岡城築城以前に居城としていた名島城の遺構です。その後、移設や転用を経て現在の位置に落ち着き、今では福岡城の一部として見ることができます。

その近くには、黒田家の重臣・母里太兵衛(もり たへえ)の邸宅に使われていた長屋門が残されています。母里太兵衛といえば、日本三名槍の一つ「日本号」を手にした武将として有名で、豪胆な武勇で知られています。

ここから坂道を上り、本丸へと向かいます。

最初にたどり着くのは「二ノ丸」です。現在は梅園として整備されているので、梅の咲く季節には、また違った景色を楽しめそうです。

二ノ丸から階段を一つ上がると、本丸に到着します。かつてここには本丸御殿が建っていましたが、政務は主に三ノ丸の御殿で行われていたため、本丸御殿は儀礼用の施設として使われていたそうです。

福岡城には大天守のほかに、小天守と中天守が設けられていたそうです。大天守と小・中天守の天守台が本丸の中央部に並び、南北を分断するような形になっており、全国的にも珍しい構成の城郭となっていました。

大天守の天守台へは、こちらの石段から登ります。ちなみに、この天守台の上に実際に天守閣が建っていたかどうかは、現在もはっきりとはわかっていないそうです。

こちらが天守台の上からの眺めです。標高はおよそ36メートルあり、福岡市街を眺めることができました。

天守台の裏側から坂を下っていくと、「多聞櫓」があります。この櫓は福岡城築城当時から残る貴重な現存建築で、国の重要文化財にも指定されています。長く続く櫓の姿から、往時の城郭の防御機能を感じ取ることができます。

二ノ丸跡地にある野球場をぐるりと回ると、福岡城の天守や城郭全体の姿を眺めることができます。黒田家が築いた城らしく、石垣や曲輪の配置が巧みに設計され、防御を強く意識した構造になっていることがよくわかります。

そのまま歩いて上之橋まで進み、ここから下城しました。上之橋側の濠は一面が蓮で覆われており、歴史ある石垣と相まって独特の風情を感じさせてくれました。

かつて筑前52万石を領した黒田氏の居城だけあって、福岡城は非常に大規模で圧倒されました。また、福岡市には福岡城以外にも黒田家ゆかりの名宝も多く残されており、日本三名槍のひとつ「日本号」や、黒田官兵衛が愛用した名刀「へし切り長谷部」などは、福岡市博物館で実際に見ることができます。
戦国時代や黒田家の歴史に興味がある方は、福岡グルメを楽しむついでに、ぜひ福岡城にも足を運んでみてはいかがでしょうか。