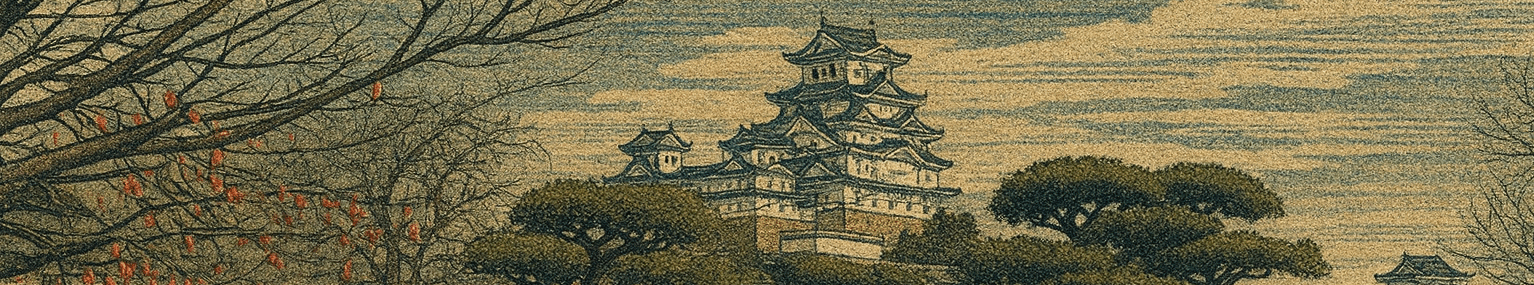日本最大級の城郭、かつて江戸幕府の中枢として機能した江戸城に行ってきました。
江戸城は「内郭」と「外郭」からなる広大な構造を持っていましたが、現在、城郭として残っているのは内郭の一部です。その内郭も大部分は現在の皇居となっていますが、本丸跡などの一部区域は「皇居東御苑」として一般公開されており、自由に見学することができます。
まずは、東京メトロの桜田門駅を降りてすぐの場所にある「桜田門」へ向かいました。
この門は、1860年に大老・井伊直弼が暗殺された「桜田門外の変」の舞台としても有名です。現存する江戸城の城門の中では、桜田門が最も大きく、重厚な造りが当時の威厳を今に伝えています。

桜田門をくぐると、石垣越しに丸の内の高層ビル群がそびえ立つ様子が目に入ります。歴史的な城郭と現代的な都市風景が隣り合わせに存在するのは、都心の真ん中に位置する江戸城ならではの光景です。

皇居正門前にかかる石橋の向こうには、「二重橋」として親しまれている鉄橋と、その奥に「伏見櫓」の姿が見えました。

そのまま皇居外苑を通ってまっすぐ進んでいくと、「巽櫓(たつみやぐら)」が見えてきます。このあたりまで来ると、徐々に石垣や櫓が現れ、城跡らしい雰囲気が感じられるようになります。

ここから「皇居東御苑」へ入園することができます。公開時間が決まっており、季節によって異なる場合もあるため、訪問前に公式情報で確認しておくと安心です。

こちらには江戸城の正門にあたる「本丸大手門」があります。かつては将軍の出入り口として使われていた重要な門ですが、関東大震災で倒壊し、現在の門は昭和期に再建されたものです。

大手門を抜けた先には「同心番所」があります。江戸時代には、徳川御三家を除くすべての大名や関係者が、ここで必ず検問を受けていたと伝えられています。

さらに進むと、「百人番所」があります。その名の通り、常時100人の同心たちが詰めていたことから、この名がついたとされています。実際、100人が待機できるだけあって建物はおよそ50メートルもの長さがあり、全体を写真に収めるのに一苦労でした。

こちらは「富士見櫓」です。かつては天守の代用とされた格式の高い櫓で、「八方正面」とも呼ばれ、どの方向から見ても同じように見える均整の取れた構造が特徴です。

こちらが江戸城の本丸です。

さすが将軍が政務を執った中枢だけあり、全国のどの城の本丸よりも広大な敷地を誇ります。かつてはこの場所に、政治の中心となる御殿のほか、大奥なども置かれていたとされています。
本丸の奥には江戸城の天守台があります。

三代将軍・徳川家光の時代には、地上約58メートルもの高さを誇る、日本最大級の天守閣がここに築かれていたといわれています。その巨大な天守を支えていただけあり、天守台自体も圧倒されるほどの大きさです。
その天守台からの眺めは、他の城のように遠くの山並みや城下町が一望できるわけではなく、目に入るのは周囲を取り囲む東京のビル群。まさに、現代都市の中心にある城跡ならではの景色です。

皇居東御苑をでて裏手にまわると、「平川橋」があります。三の丸の正門にあたる位置にあり、江戸時代には大奥への通用門としても利用されていたといわれています。

ここからは北の丸方面へ向かいます。
お堀に沿って歩いていくと、やがて「清水門」が姿を現します。

清水門の手前には、江戸時代に造られた石垣造りの水門が今も現存しています。当時の石組みがそのまま残っており、往時の城の防御機構を間近に感じることができます。

清水門をくぐると、江戸時代の姿をそのまま残す「雁木坂(がんぎざか)」が現れます。階段状になったこの坂は、当時のままの高さと幅が残されており、実際に登ることで江戸時代の人々が歩いた感覚を体験することができます。

北の丸は、現在では緑豊かな公園として整備されています。すぐ脇にある千鳥ヶ淵は、春になると見事な桜並木が咲き誇る、東京屈指の桜の名所としても知られています。

北の丸公園の北側には、「田安門」があります。江戸城に現存する建築物の中で最も古いとされており、当時の重厚な造りを今に伝えています。

江戸城跡は、外郭まで含めると現在の千代田区ほぼ全域におよぶ広さがあり、遺構も非常に広範囲に点在しています。そのため、1日ですべてを巡るのは難しく、今回は内郭を中心に見学しました。それでも回りきれないほどのスケールで、改めて江戸幕府の圧倒的な権威を感じさせられます。
皆さんもぜひ、当時の幕府の栄華に思いを馳せながら、この壮大な城跡を歩いてみてはいかがでしょうか。
日本100名城 公式スタンプ帳はこちらから。
こちらの記事もどうぞ。